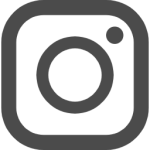【移転のお知らせ】
移転のお知らせ
いつもEDO鍼灸治療院をご利用いただき、誠にありがとうございます。
EDO鍼灸治療院は、日本橋一丁目1・2番地区第一種市街地再開発事業に伴う立ち退きにより、下記住所へ移転することとなりました。
移転後も、これまでと変わらず施術を受けていただけますので、どうぞご安心ください。
今後もスタッフ一同、皆さまの健康により一層寄与できるよう努めてまいります。
引き続き、EDO鍼灸治療院をよろしくお願い申し上げます。
■ 新住所
〒103-0021
東京都中央区日本橋本石町4丁目4−11
日本橋SSビル 1F
※電話番号に変更はありません
TEL:03-6225-2757
■ 移転スケジュール
・現店舗 最終営業日:2月26日
・新店舗 オープン日:3月3日
■ アクセス
※多方面からアクセスしやすい立地です。
【新店舗】
・JR総武本線「新日本橋駅」……徒歩3分
・JR山手線・京浜東北線「神田駅」南口……徒歩4分
・東京メトロ「三越前駅」……徒歩6分
※おすすめルート:地下道で「コレド室町テラス」内を通ると、
外を歩く時間を短縮でき、約5分で到着します。
・東京メトロ「大手町駅」B6出口……徒歩8分
(丸ノ内線・東西線からのアクセスが便利です)